浦安市議会議員 柳きいちろう
浦安市民のため誠心誠意働かせていただきたく思います!
私の希望とは「前の世代からもらったものを、次の世代へより良い状態でつなぐ」ことです。我々の子供や孫の世代に「我々の世代が良くやってくれた」という言葉を言ってもらえるようにしなければならないと強い気持ちで頑張ります。だからこそ、目先の利益にとらわれず、将来にツケを残さないという政治姿勢を多くの皆様に理解していただきたく思いますし、共有していただければと思います。
やなぎ日記
浦安市議会教育民生常任委員会 北名古屋市行政視察について 2024年5月21日
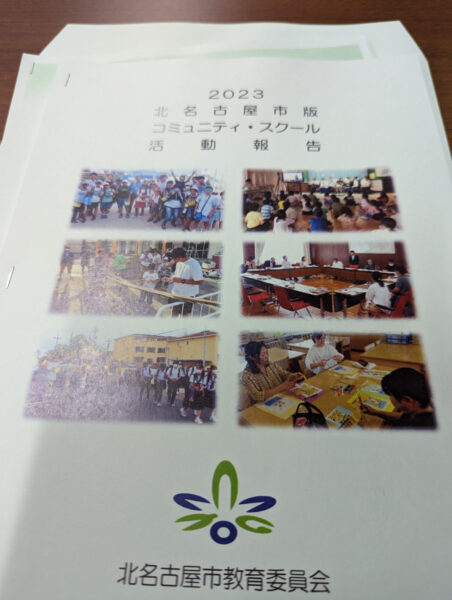
今回、公教育で重要な政策であるコミュニティ・スクールについて視察を行って参りました。
コミュニティ・スクールとは、保護者や地域の皆さんが参画する学校運営協議会を設置し、地域と学校が連携・協働しながら運営に取り組む学校のことです。学校と地域の皆さんとが、目標やビジョンを共有し、一体となって子供たちを育む、地域とともにある学校づくりが進められています。
学習指導要領では、「社会に開かれた教育課程」という方針を掲げています。日々の学習活動を進めるにも、地域をはじめとした社会の協力が欠かせません。そんな学習で育った子どもたちが社会人となり、地域・社会づくりに貢献するという好循環も期待されています。
日本が人口減少社会に突入し、自治体の消滅可能性さえ心配される中、学校と地域・保護者が手を取り合って地域社会と学校教育を担っていくためにも、コミュニティ・スクール導入の促進が求められていると言えます。
コミュニティ・スクールは、2004年の地方教育行政法改正を機に創設されました。17年に設置が各教育委員会の努力義務となってから大幅に増え、統計のある23年5月現在では全国平均で74.3%の自治体が導入しています。
そこで浦安市でもコミュニティ・スクールの推進をおこなうべく、先進自治体である北名古屋市を視察させていただきました。
今回の視察で自身が重要と思った点を備忘録として記載すると
➀コミュニティ・スクール立ち上げについては、走り出すまでは、特に教頭先生は大変だという点は免れない。
➁協議会の人員の選定について
・どうすれば一番こどものためになる地域の協力者の人選を行うかといった点
・また年齢バランスなど、長期的に持続可能な体制を構築すること
・一部の団体等に偏りなく様々なバランスを保つこと
➂教員の負担軽減について
専門的な知識を持つ学校支援ボランティアの活用や事務担当者についての導入
→東京都三鷹市などが進んでいると話されていました。
④軌道に乗れば、様々な教育活動が活性化し、こどもの成長についてつながる。こどもを通じて地域の輪を広げる。教師力の向上にもつながる。
➄コミュニティ・スクールに限らず、どこの組織もそうだが、人が変われば活性化もするし、停滞もする可能性があり、どうやってバックアップするかは重要である。
最後になりますが、快くお引き受けいただきました北名古屋市様にこの場を借りて御礼を申し上げたいと思います。
2024年05月23日
柳 毅一郎
浦安市議会教育民生常任委員会 大和郡山市行政視察について 2024年5月20日
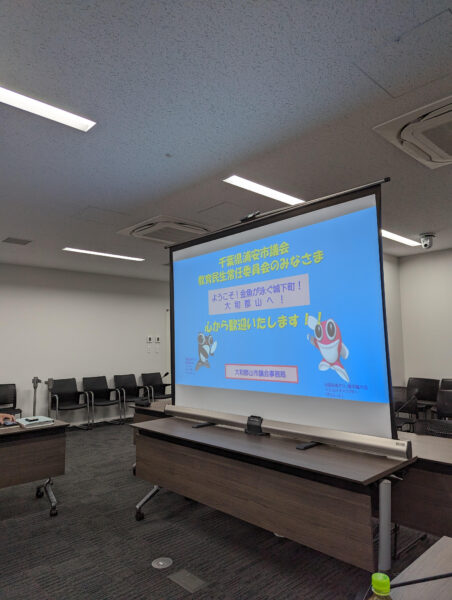

教育現場において、現在大きな課題の1つとなっているのが、児童・生徒の『不登校』です。不登校となる原因は多岐にわたりますが、近年その数が急増していることや新型コロナウイルスにより環境が変化した影響が一因であるとも指摘されています。
浦安市としてもこの問題の対策として、全ての子どもたちを現在の学校に復帰させることだけが目標でなく、子どもたち1人ひとりの実態に合わせて教育を提供する学校や学びの場を設置する必要があると考えています。
そのため浦安市では2025年4月より、学びの多様化学校(いわゆる不登校特例校)の設置を県内で初めて設置(分教室方式で)しようとしております。
そこで、先進自治体である大和郡山市を2024年5月20日に視察させていただきました。大和郡山市では、市内小・中学校に在籍する不登校児童生徒の主体的な活動を大切にしながら、社会性や相互の人間関係を築いていく力を育み、社会的自立を促す教育を推進するため、郡山北小学校・郡山中学校分教室「ASU」を設置しています。
ここでは、不登校児童生徒を対象とする学校設置に係る教育課程を弾力化できる措置を受け、学習指導要領を根本から見直し、独自の教育課程と評価を作成して、授業を進めています。
プログラムでは、適応指導教室「あゆみの広場」で得られた臨床の知を生かしながら柔軟な教育活動を展開することができるよう工夫がなされております。
浦安市で実施に当たっての課題点については
➀ 教員(県職員、市職員)や臨床心理士等、人員の確保について
今回視察させていただいて改めて理解したのは、子どもたち1人ひとりの実態に合わせて教育を提供するためには本当に人の手がかかるといったことでした。この点については浦安市に持ち帰り検討を行っていく必要があります。
➁ 独自の教育課程と評価を作成 という点
大和郡山市で分教室を設置する際には、一年程度、文部科学省とやり取りを行ったそうです。この点についてはどのような教育を行うかを考えていくかは初年度はなかなか大変ではないかと思いました。
最後になりますが、過去、浦安市議会としては2017年に大和郡山市を視察しており、今回2回目の視察となりました。浦安市長も先般に視察に参ったとのことでした。3回も視察を快くお引き受けいただきました大和郡山市様にこの場を借りて御礼を申し上げたいと思います。
2024年05月23日
柳 毅一郎
3月9日(土)に市政報告会を開催しました。


令和6年度の予算概要、事業予定、新規事業の状況などを報告させていただきました。その後、質疑応答の時間では、様々な意見や要望をいただきました。今後の市政運営の参考にさせていただきます。
3月9日の市政報告会の資料は以下でダウンロードしてください。
市政がより身近なものになるよう、今後も定期的に市の取り組みや施策を報告し、これからの市政の進め方や主要事業についての経緯経過をお話ししたいと思います。また、市民の皆さんからの質問やご意見をお受けする時間も引き続き設けます。
次回の開催については、日程が近くなりましたら、議会報告や、HP上で周知を図らせていただければと存じます。
2024年03月09日
柳 毅一郎
議会報告
柳きいちろう動画集(過去発言集) 浦安市議会 議会中継より
 柳きいちろうが過去議会で発言した動画となります。
柳きいちろうが過去議会で発言した動画となります。
お時間ありましたらご覧ください。
よろしくお願いします。
以下、時系列となります。
※柳きいちろうが議員となった平成23年からのものは、市議会HPの動画では現存しない。
無会派 (平成27年6月~平成31年3月)
こちらから
会派 20年後の街づくりの会 (令和元年6月~令和3年2月)
こちらから
会派 自由民主党・無所属クラブ (令和3年6月~令和5年3月)
こちらから
令和5年6月からは、副議長のため代表質問、代表質疑、一般質問は実施していない。
※副議長は議長に事故がある場合、代役となるため本会議で代表質問、代表質疑、一般質問をしないことが通常です。
2024年03月18日
柳 毅一郎
令和5年3月議会 一般質問を行いました。その議事録をご報告します。 件名1 2040年問題を見据えた今後の市政運営について 件名2 官学連携について 件名3 インフラ整備について 件名4 公共施設のデジタル化について

令和5年3月議会 一般質問を行いました。その議事録をご報告します。 件名1 2040年問題を見据えた今後の市政運営について 件名2 官学連携について 件名3 インフラ整備について 件名4 公共施設のデジタル化について
令和5年第1回定例会、3月15日に自身の一般質問を行いました。
※一般質問とは、議員が行政全般にわたり、市長などの執行機関に対し、事務の執行状況や将来に対する方針などについて質問したり、あるいは報告、説明を求めたりすることをいいます。
動画はこちらから
目次
件名1 2040年問題を見据えた今後の市政運営について
要旨1 高齢化の進展による課題について
細目1 2040年問題の課題認識について
細目2 老老介護や孤独死防止の取組みについて
細目3 包括的支援体制の構築について
要旨2 高齢社会における土地の問題について
細目1 地籍調査について
細目2 所有者不明土地について
細目3 空き家対策について
件名2 官学連携について
要旨1 本市の教育・研究機関との連携について
細目1 大学との連携した実績について
細目2 市内大学の各種資源の活用の現状と課題について
細目3 大学の地域貢献と学生の地域活動について
件名3 インフラ整備について
要旨1 入船地区護岸整備について
細目1 改修事業の協議状況について
要旨2 第二東京湾岸道路について
細目1 現状について
細目2 今後について
件名4 公共施設のデジタル化について
要旨1 WiFiについて
細目1 整備状況について
細目2 今後の整備の考えについて
件名1 2040年問題を見据えた今後の市政運営について
要旨1 高齢化の進展による課題について
細目1 2040年問題の課題認識について
以下、議事録となります。
○副議長(小林章宏君) 通告順により、柳 毅一郎君。
(柳 毅一郎君登壇)
◆(柳毅一郎君) それでは、今期最後の質問を行わせていただきたいと思います。初回総括、2回目以降一問一答で行います。
件名は4件となりますので、順次行わせていただきます。
まず、件名1からでございます。
急速な少子・高齢化、人口減少が進む中で、2つの大きな山があります。1つ目は団塊の世代が全員75歳に以上になる2025年問題であり、もう一つは、団塊の世代に次いで人口ボリュームの大きい団塊ジュニア世代が高齢者になっていく2040年問題と言われております。少々長いスパンの話でございますが、確実にその時はやってまいります。そのときに日本や浦安市をきちんと維持していくために、今、できることをしなければならないと考えております。
そこで重要なのは、将来で課題が大きくなりそうな時点を逆算しながら政策を進め、なぜこうした取組を進めるのかという意義や危機感をしっかりと本市としても住民に理解していただくことが大事ではないかと思っております。
そこで、2040年問題に向けての現状と課題、今後の取組について、少々テーマが大きい話になっておりますけれども、お聞かせ願いたいと思います。
件名1、2040年問題を見据えた今後の市政運営について、要旨1、高齢化の進展による課題について、細目1、2040年問題の課題認識についてです。
団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる2025年問題の先には、先ほども申したとおり、団塊ジュニア世代が高齢者となり日本の高齢者人口がピークとなる2040年問題というさらに厳しい状況が控えております。本市の人口推計や都市構造を鑑み、どのような課題を認識しているのか、まず所見を伺います。
次に、件名2、官学連携についてでございます。
要旨1、本市の教育・研究機関との連携について。
研究機関としての大学や若者が多く通う大学が近くにあるということは、自治体にとっても地域活性につながると考えております。まちづくり条例の理念である共創という事柄を踏まえ、今後、企業のみならず、大学と本市の持つ地域課題を共創して解決していくことが求められると考えております。そして今後、他地域における成功や失敗事例に学びながら浦安市として大学連携施策を進めていただきたいと願いを込めつつ、質問をいたします。
細目1、大学との連携した実績について。
これまで市内大学との包括連携協定により、浦安市はどのような成果を上げてきたのか伺います。
次に、件名3、インフラ整備について、要旨1、入船地区護岸整備について、細目1、改修事業の協議状況について。
昨年4月に管理用通路の陥没が発生した浦安海岸入船地区については、これまでに応急工事が完了し、本復旧に向けた検討を進めているところであると思います。先般、浦安海岸入船地区護岸整備懇談会が開催され、対応が検討されているところであります。そこで、浦安海岸入船地区護岸整備懇談会について、どのようなことが話し合われたのか、その内容を伺います。
次に、要旨2、第二東京湾岸道路について、細目1、現状についてでございます。
平成30年度に策定しました第二湾岸候補道路未利用地活用事業基本計画に基づいた、第二東京湾岸候補道路未利用地有効活用事業といった第二湾岸道路の土地における暫定利用も進んでおります。事業として、令和5年度では高洲地区の整備が予算化されており、市民も歓迎する大変いい取組であると考えております。
整備内容につきましては、植栽のほか遊歩道やサイクリングロードを設けて、緑道と緑道をつなげることで緑のネットワークをより充実させる整備計画であろうと考えており、ぜひ推進してほしいと考えております。代表質問で同じ会派であります西川議員からも質問がありましたが、暫定利用及び交通問題に対処していただければと思います。
さて、今回の私の一般質問では、第二東京湾岸道路について、暫定利用という観点ではなく、大局的な観点から質問を何点かさせていただきたいと思います。
それでは質問に移りますが、東京都と千葉県の湾岸部を結ぶ構想である第二東京湾岸道路の建設に向けた計画が再始動してから数年がたちますが、市長が施政方針で挙げられた新たな湾岸道路整備促進大会で本市としてどのような要望を上げたのか、ご答弁願います。
次に、件名4、公共施設のデジタル化についてです。
地方自治体がWi-Fiを提供する場合、現時点では、1つ目として観光、2つ目として防災・減災、3つ目として住民サービス向上、行政事務効率化、4つ目としてGIGAスクール以降の教育分野などの利用目的が考えられます。ここ数年でコロナ禍以降の利活用の在り方も、民間の動向も変化があるため、改めて整備について当局のお考えを聞かせていただきたいと思います。
要旨1、WiFiについて、細目1、整備状況について。
現在、浦安市の公共施設におけるWi-Fiの設置やWi-Fiルーターの貸出し場所はいかがかお伺いいたします。具体的な設置場所や貸出し施設についてお示しをいただきたいと思います。
以上、1回目の質問とさせていただきまして、以降は質問者席から行わせていただきます。
よろしくお願いいたします。
○副議長(小林章宏君) 市長、内田悦嗣君。
(市長 内田悦嗣君登壇)
◎市長(内田悦嗣君) 柳 毅一郎議員の一般質問にお答えいたします。
私からは件名1、2040年問題を見据えた今後の市政運営について、この中の細項目1、2025年問題の先には2040年問題というさらに厳しい状況が控えているが、本市の人口推計、都市構造から鑑みどのような課題を認識しているのかというお尋ねでございます。
本市の人口推計では、今後、後期高齢者が全国平均を大きく上回る割合で増加することが予測されており、要介護認定者や認知症の方が増加することも見込まれております。
また、核家族が多いという、そういった世帯構成の特徴、あるいは集合住宅が多く多世代で一緒に暮らすことがなかなか難しいという、そういった住戸形態から考えますと、今後、単身や夫婦のみの世帯の高齢者ですね、こういった方が増えることも想定されておりまして、それにより社会的孤立やセルフネグレクトということの深刻化というものも懸念されているところでございます。
こうしたことから、市といたしましては高齢者が住みなれた地域で安心して暮らし続けられるよう、住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムのさらなる深化、推進に取り組んでいく必要があるというふうに認識しております。
他につきましては担当よりお答えいたします。
○副議長(小林章宏君) 企画部参事。
◎企画部参事(町山幹男君) 私からは1点、件名2、官学連携について、要旨1、本市の教育・研究機関との連携についての中、これまで市内大学との包括連携協定による成果等のお尋ねです。
これまで包括連携協定等を締結している市内の明海大学、順天堂大学、了徳寺大学の3大学とは、各種委員会、審議会への委員としての参加をはじめ、浦安市学生防犯委員会V5による防犯や啓発活動、小学校での学習支援や教育実習など、様々な連携事業を実施してきたところです。
このように、知的資源、人的資源や人材の育成など、包括連携により豊かな地域社会の発展に寄与してきたと考えております。
以上です。
○副議長(小林章宏君) 都市整備部長。
◎都市整備部長(知久岳史君) 私からは、1点についてお答えいたします。
件名3、インフラ整備について、要旨1、入船地区護岸整備についての中、浦安海岸入船地区護岸整備懇談会について、どのようなことが話し合われたかというお尋ねです。
浦安海岸入船地区護岸整備懇談会につきましては、護岸の管理者である県より、管理用通路が陥没に至った経緯や現況調査結果、及び応急補修の実施状況などの説明の後に、護岸復旧の対策工法案が示されました。
その後、学識者、漁業関係者、地域住民、行政関係者により、対策工法案や、同じく三番瀬に面した日の出地区や市川塩浜地区との護岸形状の違い、また、景観面への配慮や完成後の利活用などについて意見交換が行われました。
私からは、以上です。
○副議長(小林章宏君) 都市政策部長。
◎都市政策部長(板橋栄一君) 私からは、1点お答えさせていただきます。
件名3、インフラ整備について、要旨2、第二東京湾岸道路についての中、新たな湾岸道路整備促進大会で、本市としてどのような要望を上げたのかとのお尋ねになります。
(仮称)新たな湾岸道路につきましては、湾岸部の広域的な道路ネットワークを早期に示すことや、本市の住宅都市としての特性を十分踏まえた計画とすること、また、国道357号の渋滞対策について確実に事業を促進するよう要望を上げたところでございます。
以上でございます。
○副議長(小林章宏君) 総務部長。
◎総務部長(山崎勝己君) 私からは1点、件名4、公共施設のデジタル化について、要旨1、WiFiについての中、市の公共施設におけるWi-Fiの具体的な設置場所と、Wi-Fiルーターの貸出し施設についてのお尋ねです。
公衆無線Wi-Fiの設置につきましては、庁舎や総合福祉センター等の公共施設で10か所、公民館や図書館の生涯学習施設で11か所、文化会館や音楽ホール等の文化施設で3か所、総合公園や交通公園等の公園で4か所、合計28か所に設置しています。
また、Wi-Fiルーターにつきましては、全ての公民館で施設利用者に貸出しを行っております。
以上です。
○副議長(小林章宏君) 柳 毅一郎君。
◆(柳毅一郎君) ありがとうございます。それぞれ皆様、ご答弁ありがとうございました。
それでは、2回目の質問を行います。
件名1の中、細目1、2040年問題の課題認識についてでございます。
先ほどは市長より答弁いただきまして、ありがとうございます。おっしゃるとおりだなというふうに思いますので、本当に着実に、ちょっと先のスパンの話を振ってしまいましたというか、質問させていただきましたけれども、しっかりと取り組んでいく必要があろうかという課題認識を持っております、私も。
そこでもう一度、浦安市の2040年までの人口推計を見ながら、やはりこの事態を、住民と意識を共有しながら行く必要があるのではないかと思います。2040年の浦安市の姿を具体的に明示した上で今後の施策を推進すべき、そういうような、目に見えるような形で推進していく必要があるのではないかと私は考えております。そしてまた、将来を逆算しながら、2040年頃にかけて顕在化する変化、課題について何かしらの対応を図る必要があると思いますが、一定市長からも答弁いただきましたけれども、通告しておりますので、ご答弁をよろしくお願いいたします。
○副議長(小林章宏君) 福祉部長。
◎福祉部長(高梨誠二君) 市では現在、地域包括ケアシステムをさらに深化、充実させることを目指し、令和6年度から8年度までを計画期間とする次期高齢者保健福祉計画と、第9期介護保険事業計画の一体的な策定に取り組んでいるところです。
計画の策定に当たりましては、2040年にかけて顕在化することが見込まれる変化や課題を見据えつつ、介護サービス基盤を計画的に整備するなど、中長期的な視点にも立ちながら策定作業を進めてまいりたいと考えております。
○副議長(小林章宏君) 柳 毅一郎君。
◆(柳毅一郎君) 具体的な答弁、ありがとうございます。
ぜひ、やはり人口比というのはなかなか、そうそう変化がないと思いますので、やはり一番大変な頃を見据えてやっていただくことが重要ではないかというふうに考えております。
続きまして各論点に移りたいと思いますが、細目2、老老介護や孤独死防止の取組についてでございます。
老老介護というのは皆さんも耳に、聞いたことが当然あろうかと思いますけれども、主に65歳以上の高齢の夫婦や親子、兄弟などが、どちらかが介護者であり、もう一方が介護されることを指します。高齢社会が進展すれば当然数も多くなってくる事柄ではないかと思いますけれども、本市の現状をまず確認させていただければと思います。
老老介護について本市の状況はどのようなものとなっているのか、元町、中町、新町、各地区について所見を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
○副議長(小林章宏君) 福祉部長。
◎福祉部長(高梨誠二君) 令和元年度に実施いたしました介護保険実態調査の結果によりますと、主な介護者の年齢が60歳以上と回答した方の割合は市全体で約53%、地域別では元町が48%、中町が61%、新町が60%となっております。
これらの値は、令和2年に国が公表した2019年国民生活基礎調査の概況による全国の60歳以上同士の介護の割合、約74%と比較すると低くはありますが、今後、本市では急速に高齢化が進む見込みであることを考えますと、いわゆる老老介護のケースも増加していくものと推測されます。
以上です。
○副議長(小林章宏君) 柳 毅一郎君。
◆(柳毅一郎君) ありがとうございます。
続きまして、孤独死に関してでございます。
孤独死については、私としては、独り暮らしをしていて誰にもみとられず亡くなった場合を想定し、通告をさせていただきました。しかしながら、本件通告後に担当課より、厚生労働省の定義に基づくと「孤独」は主観的な概念であり、独りぼっちと感じる精神的な状態を指し「寂しいということ」という感情を含めて用いられることがあり、他方「孤立」は客観的概念であり、社会のつながりや助けのない、または少ない状態を指すとのご指摘がありました。なかなか難しい言葉だと思うんですけれども、通告に「孤独死」としましたけれども、客観的概念である「孤立死」として話を進めたほうが適切ではないかと思いますので、その用語で進めさせていただきたいと思います。
孤立死は、当然のことながら私、皆さんも……、言葉のあれですけれども、当然のことながら高齢単独世帯の住民の確率が高いと思います。本市の令和元年の人口推計を見ますと、こちらは総合計画に載っていたものなんですけれども、高齢者のいる世帯のうち65歳以上の高齢単独世帯は、令和37年--2055年には1万7,731世帯となって、世帯比率で20.7%に達すると見込まれております。また、75歳以上の単独高齢世帯も同じく2055年には1万4,282世帯となり、世帯比率で16.6%に達するというデータがございます。
先ほど市長からありましたが、やはり本市としては埋立地を開発した歴史、そして集合住宅、いわゆる団地が多い都市構造を持っております。そして核家族がすごく多いという都市構造を持っており、やはりこの独り暮らしの増加というのは潜在的な課題ですし、もう既に顕在化しているのではないかと思っております。
そして今後、やはり問題はさらに深まると考えておりますが、高齢者単独世帯の増加が見込まれ、必然的に孤立死も増えることが想定されますが、こういった孤立死が増加することによって本市にどのような影響を与えるのか、当局に見解をお聞きしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
○副議長(小林章宏君) 福祉部長。
◎福祉部長(高梨誠二君) 家族や近隣住民との関わりが希薄で社会から孤立した状態のまま亡くなる孤立死は、死後長期間経過してから発見されることが多く、本人自身の人間としての尊厳が損なわれるのみならず、家族や近隣住民への心理的な影響や、ケースによっては周辺住宅の資産価値などへの影響が生じるものと考えられます。
以上です。
○副議長(小林章宏君) 柳 毅一郎君。
◆(柳毅一郎君) ありがとうございます。
そこで、対策について何点か聞きたいと思うんですけれども、まず、孤立死対策として、本市の見守りネットワークについて伺いたいと思います。
こちらについては、認知症による徘回や自宅内で倒れている可能性があるなど高齢者の異変を見つけた場合、市へと連絡をいただくことにより早い段階で対応を行える体制を構築する、そういった事業でありますけれども、この事業がどの程度効果があったのか、所見を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
○副議長(小林章宏君) 福祉部長。
◎福祉部長(高梨誠二君) 本市における高齢者見守りネットワーク事業の協力事業者数は、事業を開始した平成26年度は33団体でしたが、令和5年2月3日現在、予定も含めますと65団体と、ほぼ倍増している状況です。また、協力事業者の業種についても、郵便局や宅配業者をはじめ電気・ガス事業者、新聞販売店、金融機関、生協など幅広い業種の方々にご協力をいただいており、地域におけるさりげない見守りのネットワークが広がりを見せていると認識しております。
○副議長(小林章宏君) 柳 毅一郎君。
◆(柳毅一郎君) ありがとうございます。
団体数が倍増しているということで、市としても頑張っていただいているのかなというふうに認識させていただきました。
そこで、まずこのネットワークについて伺わせていただいたんですけれども、やはり孤立死の防止というのは、私も思うところがありますけれども、やはり基本的には自治会とか、そういう顔の見える関係で、地域交流があることが前提ではないかというふうに思っております。そういったところも当然やっていかなければいけないところだと思いますけれども、様々な取組も、やはり見守りの担い手不足とかそういったことも考慮する必要があるのではないかと考えております。
単身高齢者の見守りや、民生委員のなり手不足といったものもやはり全国的な課題であると考えております。やはり官民連携で、警備会社と連携しながら対処する自治体も出てきております。本市でも高齢者緊急通報装置貸与事業が行われていますが、この官民連携事業として行われた事業について、利用者数や利用者の声などを踏まえ、効果について見解を伺いたいと思いますが、よろしくお願いいたします。
○副議長(小林章宏君) 福祉部長。
◎福祉部長(高梨誠二君) 緊急通報装置貸与事業につきましては、令和5年1月末現在で1,160名の方にご利用いただいており、昨年度末時点と比較すると82名増加している状況です。
利用者の声としましては、万が一自宅で体調が悪くなったときでも装置があると安心できるといったものや、緊急でないときも、相談ボタンから健康相談ができ助かっているとの声が寄せられております。
なお、月に20件程度ある通報のうち、約4分の1は救急車の要請に至る緊急的なものであり、高齢者が不安軽減にとどまらず、命を守るためにも装置が有効活用されているものと考えております。
○副議長(小林章宏君) 柳 毅一郎君。
◆(柳毅一郎君) ありがとうございます。
やはりなり手、担い手というか、見守るというのもなかなか大変なことではないかと思いますので、民生委員のなり手不足とかそういったところも将来的にはいろいろカバーして、こういった事業でやっていかないといけないのかなというのがいろいろ考えた上で私も思ったところでございまして、質問をさせていただいております。こちらについてはぜひ今後、総合的に検証を図りながら、効果等をはかっていただきながら推進していってもいい事業ではないかなというふうに思っております。
そこで、高齢者緊急通報装置について、まず、たしか1,160名ですか、すみません、大体その程度だったと思いますけれども、利用者がいるということなんですけれども、どの程度市民に認知されているのか、また、必要な高齢者に対し現在の周知方法をお聞きした上で、周知の課題点について見解を問いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○副議長(小林章宏君) 福祉部長。
◎福祉部長(高梨誠二君) 本事業の周知につきましては、ホームページや広報紙、シニアガイドブックへの掲載により実施しているほか、地域包括支援センターやケアマネジャー、民生委員活動等を通じた日常的な相談、支援の中で、装置が特に必要と判断された方に個別に利用を呼びかけるなどの取組も行っているところです。
一方で、近年、民間も含め高齢者に提供されるサービスが多様化し、サービスに関する情報も増える中で、見守りを必要とする高齢者にいかに的確に情報を届けられるかが課題と認識しております。
○副議長(小林章宏君) 柳 毅一郎君。
◆(柳毅一郎君) ありがとうございます。
この孤立死とか老老介護といった問題は、当然今、言ったことで解決すべき問題というか、総合的にやらないといけないところではないかと思いますけれども、今回私の見解等を、推進してほしいといったことで述べさせていただきました。ありがとうございます。
次に、先ほど申しておるところなんですけれども、細目3の、包括的支援体制の構築についてでございます。
冒頭に申したとおりなんですけれども、2040年といった時期に向けて、段階的に包括的支援体制を構築する必要があろうかと思います。これがやはり重要な事業ではないかと思いますが、実施計画でもこの包括ケアについて盛り込まれているところなんですけれども、高齢者やその家族が身近な場所で気軽に相談できるよう、地域包括支援センター及びサテライトの適正配置を検討し、増設やサテライト事業の拡充を図りますとございます。今後の事業展開について改めてお伺いさせていただきます。
○副議長(小林章宏君) 福祉部長。
◎福祉部長(高梨誠二君) 地域包括支援センターの増設及びサテライト事業の拡充につきましては、次期介護保険制度改正の動向も踏まえつつ、今年度実施している地域包括支援センター・サテライト配置検討事業の結果を基に将来的な考え方や配置場所、箇所数等を決定し、次年度策定する第9期浦安市介護保険事業計画に位置づけ、計画的に進めていきたいと考えております。
以上です。
○副議長(小林章宏君) 柳 毅一郎君。
◆(柳毅一郎君) ありがとうございます。
今回の中で、改めて2040年といったことについても議場の中で一定の、何というんですかね、認識が共有されて、あと計画等にも入れていただけるといったようなことがありました。本当に、早いもので私も12年目になりましたけれども、こんなにすぐ12年たつとは思わなかったぐらい早くて、2040年という時期も遠いようで近くにというか、確実にそのときはやってくると思いますので、どうか皆様よろしくお願い申し上げます。
続きまして要旨2、高齢社会における土地の問題についてでございます。
少子・高齢化の人口減少が抱える課題の1つとして、土地や住宅余りが指摘されております。本市は交通アクセスの面から極めて有利な条件を有しておりまして、非常に、私も一市民として魅力のあるまちではないかというふうに思っております。ただし、社会的趨勢として高齢社会に係る土地や住宅の課題が起こる可能性はあり、動向を注視してほしいという観点から質問をさせていただきます。
今後、土地にまつわる課題が増えることや、空き家により地域の魅力が低下するといった事態を、行政ができることを行うことで可能な限り縮小することを願い、質問させていただきます。
まず、細目1、地籍調査についてでございます。
地籍調査については、こちらについてはもちろん震災の関係の、液状化被害で分からなくなった土地の境界確定に対応することを主として行われまして、中町・新町地区で行われました。その副次的効果というところから質問させていただきたいと思うんですけれども、人口減少、高齢化の進展等により人証、いわゆる人的証拠ですね--が失われてしまう前に、境界の明確化ができ、相続が円滑に行われる等が考えられます。改めて地籍調査について、今後の高齢社会の土地問題に多少なり寄与するのか、当局の見解をお伺いしたいと思います。
○副議長(小林章宏君) 都市整備部長。
◎都市整備部長(知久岳史君) 本市の地籍調査事業につきましては、東日本大震災の液状化現象によって不明確となった土地の境界を明らかにすることを目的としています。地籍調査により登記が完了しますと、土地取引や相続が円滑にできるようになり、個人資産の保全及び地域の安心につながることから、高齢社会における土地問題の一助になるものと考えております。
以上です。
○副議長(小林章宏君) 柳 毅一郎君。
◆(柳毅一郎君) ありがとうございます。
また、相続関係の法規が変わってくるといったところもいろいろ、ちょうど今回のタイミングだというところでも聞かせていただきたいんですけれども、所有者不明土地ということで、当然浦安市は新町・中町地区といったところは埋立てなので、そういったところはなかなか少ないのかなというところで、そういう前提の中なんですけれども、いわゆるこの「所有者不明土地」というのは、国交省の定義によると、相続等の際に土地の所有者について登記が行われないなどを理由に、不動産登記簿を確認しても所有者が分からない土地、また、所有者が分かっていてもその所在が不明で所有者に連絡がつかない土地を指すと定義があります。
こちらは地方の問題ではいろいろ言われているところなんですけれども、東京など都心部でも一定その課題があると聞きます。本市の状況についてはどのようなものとなっているのか、状況についてお伺いいたしたいと思います。
○副議長(小林章宏君) 財務部長。
◎財務部長(泉澤昭一君) 所有者不明の土地の状況につきましては、土地に係る固定資産税の課税の状況から申し上げますと、納税義務者となる土地所有者が不明となっている土地は、現在ございません。
なお、相続人が存在しないため課税を保留している土地は、9筆というふうになっております。
○副議長(小林章宏君) 柳 毅一郎君。
◆(柳毅一郎君) ありがとうございました。
こちらについてもちょっと、どういう状況かということをまず聞かせていただいたということになりますので、ご答弁のほどありがとうございました。
続きまして細目3、空き家対策についてでございます。
本市の都市計画マスタープランには「これまで、堅調な人口増加を支えていた埋立地における大規模な住宅団地の開発が終盤を迎え、人口の伸びの鈍化傾向が強まるとともに、地区によっては住民の高齢化と住宅の高経年化が進行することで、今後、住宅の管理不全化や空き家問題の増加も懸念されることから、既存の住宅ストックの活用に加え、まちづくりのルールの運用による良好な住環境の維持保全などを通じて、住宅地の魅力を向上させる必要があります」と書いております。
浦安市のこの地域課題となる空き家について、先ほど申したとおりなんですけれども、総体的には本市というのは非常に魅力のある地域ではないかというふうに思っております。また、空き家については県内では一番低いというふうなことは重々承知しておるんですけれども、そういったマスタープラン等々に記載もありますので、今後についてどのような影響があると考えるのか、当局の見解をお示しいただきたいと思います。
○副議長(小林章宏君) 都市政策部長。
◎都市政策部長(板橋栄一君) 少子・高齢化のさらなる進展により、高齢者のグループホームなどの施設への転居や入院などによる空き家の増加に伴い、その維持・管理や活用が困難になることで管理不全の空き家が増加することや、また、所有者が死亡した後の権利継承者の特定が困難な空き家が増加することなど、課題があるものと認識しております。
以上です。
○副議長(小林章宏君) 柳 毅一郎君。
◆(柳毅一郎君) ありがとうございます。
いろいろ今、述べていただいたんですけれども、今後、何というんですか、直球というかそのままなんですけれども、空き家対策について、本市が考えている今後の取組についてご答弁願いたいと思います。
よろしくお願いします。
○副議長(小林章宏君) 都市政策部長。
◎都市政策部長(板橋栄一君) 令和3年3月に策定した浦安市空家等対策計画に基づき、現在実施している情報提供や住まいの講習会など、空き家に対する意識の醸成を図る取組を継続するとともに、所有者の特定をはじめ助言や指導など、管理不全な空き家の解消の効果的な実施に向け、関係団体と連携を図りながら仕組みづくりに取り組んでまいります。
以上です。
○副議長(小林章宏君) 柳 毅一郎君。
◆(柳毅一郎君) ありがとうございます。
高齢化について、関係していろいろ聞かせていただきました。最後は空き家ということで、やはり本市というところで、るる申しているんですけれども、やはり浦安市のことを考えると住宅都市というイメージが私はすごく強くて、当然オリエンタルランド社等々、テーマパーク等もございますけれども、浦安市が何で発展したかというふうに言えば、やはり利便性がよくて、住宅地としての開発がすごく成功したというイメージがありますので、そこを考えると、やはり住宅をいかにいい環境で提供するかといったことが本市にとって今後の非常に重要な取組ではないかと思いますので、改めて、有利な条件にはあると思いますので、ぜひご一考いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
次に件名2、官学連携について、要旨1、本市の教育・研究機関との連携について、細目1、大学との連携した実績についてでございます。
冒頭に述べましたとおり、まちづくり条例の理念であります共創という事柄を踏まえ、今後、企業のみならず、本市と大学と様々なところと、様々な団体とコラボしてというか、共創して解決していくことが必要ではないかと思います。そこで、この連携協定に期待される取組について、取り組んでいきたい事柄や期待される事柄について当局のお考えをお聞きしたいと思います。
よろしくお願いいたします。
○副議長(小林章宏君) 企画部参事。
◎企画部参事(町山幹男君) 浦安市官民連携に関する基本方針において、民間の1つである大学とも連携・協力を図り、互いの強みを生かし、補完し合うことによって最適な行政サービスの提供を実現し、地域の価値や住民の満足度の最大化を図ることとしております。このため、これまでの包括連携協定を有効に活用しつつ、市や市内大学が共通する地域課題の解決に向け、さらに取組を進めていく必要があると考えております。
以上です。
○副議長(小林章宏君) 柳 毅一郎君。
◆(柳毅一郎君) ありがとうございます。ぜひ、よろしくお願いいたします。
次に、細目2に移ります。市内大学の各種資源の活用の現状と課題についてでございます。
今現在、市内にある各種資源の活用について本市はどのように考えるのか、この大学の資源ということですね、見解をお伺いしたいと思います。
○副議長(小林章宏君) 企画部参事。
◎企画部参事(町山幹男君) 市内各大学との知的・人的・物的資源などについて取り組んでいる連携事業としては、各種委員会、審議会への委員としての参加、ボランティア活動や教育実習、施設の市民への開放として災害時の指定避難所や図書館の利用などとなっております。
このように市内大学の各種資源を活用することは、本市の発展に大きく寄与するものと考えており、今後も引き続き、新たな資源の活用も含め、必要な連携事業を推進していきたいと考えております。
○副議長(小林章宏君) 柳 毅一郎君。
◆(柳毅一郎君) 前向きなご答弁で、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。
そこで、続きまして、市内大学の各種資源の活用に当たっての課題認識についてお伺いしたいと思います。
よろしくお願いいたします。
○副議長(小林章宏君) 企画部参事。
◎企画部参事(町山幹男君) これまで市内各大学とは、市と個別の連絡協議会などを開催しながら連携事業の推進を図ってきておりますが、これら個別の連携事業だけでなく、市や市内大学に共通する地域課題の解決に向けた取組も進めていく必要があると考えております。
このようなことから、令和5年1月に浦安市・市内大学連絡協議会を設置し、市と市内3大学間のネットワークの強化を図り、地域の課題への対応などを共有しながら、より多様かつ特徴を生かした連携事業を実施していきたいと考えております。
以上です。
○副議長(小林章宏君) 柳 毅一郎君。
◆(柳毅一郎君) ありがとうございます。
今、1対1から、市内3大学との協議会を持つといったような答弁があったと思います。ぜひ、新しい取組であると思いますので、なかなか、何というんですかね、すぐに何かを求めるわけではないんですけれども、ぜひ、つくりましたまちづくりの条例等の理念を基に、やはり冒頭に申したとおり、大学というのは研究機関というのもそうですし、大学生、非常に若い人が集う場でありますので、何か新たなことができたらすばらしいのではないかという観点を込めて質問させていただきました。
続きまして、細目3に移ります。大学の地域貢献と学生の地域活動についてでございます。
こちらについては、やはり何かの縁があって浦安市に居を構えるといいましょうか、立地しております大学に通う大学生でございますので、何か本市と共に共創してほしいなというふうに考えております。
いろいろ可能であればということで、なかなか大学生も忙しいとは思いますので、全てできるというわけではないんですけれども、何か大学生と大学教員が地域の中に入って、この間の東京芸大のようなものもありましたけれども、そういったような形で、地域の住民や団体と共に地域の問題解決ということを何か継続的にできれば、私はすばらしいのではないかなというふうに思っております。あと、やはりそういうものがあるとまちに元気が出てくるような気がしてなりません。
そこで、そういった中で、市内の大学生等を募ることもできるとは思うんですけれども、やはり個別にボランティアを募るより大学単位でボランティアといいましょうか、そういうまちづくりというか、浦安市のことを考えてくれるという学生を集めるほうが活動が活発になると思われます。大学生にとってもよい社会体験になるのではないかというふうに思っておりますが、本市で大学生の力を活用する場を設けることについて、実績及び見解を求めたいと思います。
よろしくお願いいたします。
○副議長(小林章宏君) 市民経済部長。
◎市民経済部長(杉山正毅君) 市内にある大学のうち、明海大学とは平成14年10月に明海大学学生の社会貢献活動の推進に関する協定を締結し、公共施設等においてボランティアの受入れを行っております。
令和4年度の実績としては、図書館での書架整理、保育園での運動会の準備、青少年交流活動センターや、こどもの広場での子供の見守りなどのボランティア活動を行いました。
本市としても、学生のボランティア活動は地域における福祉の向上と学生の社会貢献意識の高揚に寄与することから、今後も受入れを継続していきたいというふうに考えております。
以上です。
○副議長(小林章宏君) 柳 毅一郎君。
◆(柳毅一郎君) ありがとうございます。
その中で1点お伺いしたいのですけれども、やはりこの学生を集めるといったところでも、自身の大学の学生時代等を考慮しても、なかなか学生というのも時間がないというところもあったりとかして、やはりうまく仕組みをつくる必要があろうかと思いますけれども、こちらについて、学生に浦安市のまちづくりの取組に参加してもらうに当たって単位認定がされるインセンティブが必要になろうかと思いますが、そのあたりについて現在、市はどのような取組を行っているのかご答弁願いたいと思います。
○副議長(小林章宏君) 市民経済部長。
◎市民経済部長(杉山正毅君) 明海大学では、学生時代に貴重な経験を得るための動機づけとして、また真摯な活動に対する正当な評価であるとの見解から、一定時間以上のボランティア活動に対し単位認定の制度を設けているところです。
以上です。
○副議長(小林章宏君) 柳 毅一郎君。
◆(柳毅一郎君) やはり必要な取組ではないかと思います。
今の質問をしたのは、次の質問にも関連するんですけれども、やはり若者の意見を市政に反映できないかなという大きなテーマがあります。中学生、高校生といったところもあるんですが、当然それもいいと思うんですけれども、より大人の中で意見が欲しいというか、ぜひ市政に様々、何を望んでいるのかということを把握することは市としても重要なことではないかと思います。
そこで、そういった中で、やはり単位認定等があったほうが学生も本気で取り組むのではないかなというふうに思って質問させていただきました。すみません。
それでは質問に戻りますけれども、是非そういった若者の意見をもっと市政に反映できないかと私も考えておりますが、市内大学生による本市に対する意見の吸い上げについて、見解を伺いたいと思います。
○副議長(小林章宏君) 企画部参事。
◎企画部参事(町山幹男君) 市は、これまでも「市長への手紙」やパブリックコメントなどにより多くの市民の皆様からのご意見やご要望をお聞きしてまいりました。
市内大学生の市政への参加の機会につきましては、今後もこれまでと同様の取組を進めるとともに、市内大学連絡協議会で協議してまいりたいと考えております。
以上です。
○副議長(小林章宏君) 柳 毅一郎君。
◆(柳毅一郎君) ありがとうございます。
やはり、少子化の影響もありまして、だんだん若い世代というのはどんどん少なくなっております。そして、やはり積極的に声を上げるという形よりも、最近の学生はおとなしい--と言ったら失礼かもしれないですけれども、私もそのおとなしい中の1人かもしれなかったんですけれども、そういう仕組みがないと、そういうことを聞く機会もなかなかないのかなというふうに思いますので、ぜひ検討していただければと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
件名3、インフラの整備についてでございます。
要旨1、入船地区護岸整備について、細目1、改修事業の協議状況についてでございます。
先ほどは、懇談会の内容についてお聞かせ願いました。
そこで、具体的に本市の護岸の修繕について、どのような復旧方法を検討しているのかお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○副議長(小林章宏君) 都市整備部長。
◎都市整備部長(知久岳史君) 護岸改修につきましては、市民の生命や財産を高潮や波浪、津波などの水害から守ることを目的として、三番瀬や猫実川河口部の環境に与える影響のほか、後背地の状況等にも配慮しながら県において検討を進めています。
また、具体的な復旧方法につきましては、施工性がよく早期完成が見込めることや、海側への張り出しが最小限で騒音や振動による環境への影響も少ないことなどから、旧江戸川の護岸工事でも用いられている自立鋼管矢板式の直立型護岸を最適案として考えていると県から伺っております。
以上です。
○副議長(小林章宏君) 柳 毅一郎君。
◆(柳毅一郎君) ありがとうございます。
それでは、この細目については最後となりますけれども、当該地域は早急に工事を必要とするものと考えておりますが、今後、県とどのようなスケジュールで工事を進めていくのかお伺いいたします。
○副議長(小林章宏君) 都市整備部長。
◎都市整備部長(知久岳史君) 改修工事のスケジュールにつきましては、護岸の構造形式の決定を令和5年3月末までに行い、工事着手に向けた住民説明会を行った後に、夏頃までには資材搬入路や工事ヤードの整備といった準備工事、また、秋から冬頃には本体工事に着手する考えであると県から伺っております。
以上です。
○副議長(小林章宏君) 柳 毅一郎君。
◆(柳毅一郎君) ありがとうございます。
護岸については本市の本当に極めて重要な事業だと思いますし、とにかくこの事業は着実に進めていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。
続きまして、同じく件名3の中、細目2、今後についてでございます。
先ほど本市の要望について聞かせていただきましたが、続きまして、期成同盟での協議内容について聞かせていただきたいと思います。新たな幹線道路期成同盟会では今後どのような予定で計画がなされているのか、その内容について、現時点で分かっているものについてお聞かせ願いたいと思います。
よろしくお願いします。
○副議長(小林章宏君) 都市政策部長。
◎都市政策部長(板橋栄一君) (仮称)新たな湾岸道路期成同盟会につきましては、これまで県と国、沿岸6市が一丸となり道路の整備実現に向け機運を高めてきたところであり、今後、早期に期成同盟会を設立する予定となっております。
以上です。
○副議長(小林章宏君) 柳 毅一郎君。
◆(柳毅一郎君) すみません、相手があるところでなかなか答弁しづらいところだったかもしれませんけれども、最後にこちらもちょっと、本市単独でやっているわけではないので難しいところを通告してしまいましたけれども、現在、先ほど申したとおりですけれども、道路の未利用地有効活用事業が行われていると思います。こちらについては私も大変評判がいいと聞いておりますし、単純に、やはりぼうぼうとしていた草の所がきれいになっていくというのを見るのはすごく、一住民としても「あ、いいな」というふうに思っております。
そこで、ちょっと大局的な話で恐縮なんですけれども、その修景整備が今後どうなっていくのかという、その全体計画があるのかどうかというのを聞きたいと思います。
この第二湾岸道路の全体の大局的な全体計画と、この第二東京湾岸候補道路未利用地有効活用事業の推進における整合性といったものは取られているのか、また、どのように考えられているのか、見解があればお示しいただければと思います。
○副議長(小林章宏君) 都市政策部長。
◎都市政策部長(板橋栄一君) 未利用地については、第二東京湾岸候補道路の全体計画が見えないことから、ルートを具体化していく中で必要に応じて対応できるような暫定整備を行い、有効活用していく考えです。
以上です。
○副議長(小林章宏君) 柳 毅一郎君。
◆(柳毅一郎君) ありがとうございます。
なかなかこの第二湾岸道路のところにつきましては、これもかなり長いスパンになる話だと思いますけれども、定点的といいましょうか、関心もやはり強くて、もしそれが開通した場合、どういう形で開通するかにもよるかもしれないんですけれども、相当本市は影響を受けるものと考えておりますので、引き続き聞かせていただいたり、注視していきたいと思います。ありがとうございました。
次に、最後の件名となります。公共施設のデジタル化についてでございます。
要旨1、WiFiについて、細目1、整備状況についてでございます。
先ほどは本市の基礎的なデータとして、Wi-Fi整備の状況について伺わせていただきました。ここから少し各論的になってきますが、災害時の対応について見解を伺いたいと思います。
教育施設のGIGAスクールのいい影響だと私は考えておりますけれども、学校ではWi-Fiがすごくしっかりと準備、整備されたと思っております。実際整備されていると思います。こういった学校施設を含め、本市の災害時の避難の際に、平時ではなく災害時でも活用できる環境にあるのかお伺いしたいと思います。
よろしくお願いいたします。
○副議長(小林章宏君) 教育総務部長。
◎教育総務部長(丸山恵美子君) 学校施設を避難場所として活用する際は、学習用として整備しているWi-Fi環境の設定を変更することで、避難されてきた地域住民などが使用できるようになっています。
○副議長(小林章宏君) 柳 毅一郎君。
◆(柳毅一郎君) 分かりました。
この点、どういう状況になるかというのは、災害でそういうふうに実際にということは、まだ現実ではないかと思うんですけれども、しっかりと、うまく活用していっていただきたいと思います。
続きまして教育関係のところで、公共施設で無償Wi-Fiを補完する形で、教育分野の活用として家庭学習用の通信機器整備支援事業におけるルーターの貸与が行われておりますが、活用状況と課題認識、今後の有効活用について、それぞれご答弁をいただければと思います。
○副議長(小林章宏君) 教育総務部長。
◎教育総務部長(丸山恵美子君) 学校へ貸与するためのWi-Fiルーターは、各家庭に対して必要数の事前調査を行い、国の公立学校情報機器整備費補助金を活用し、84台購入したところです。
そのうち貸出台数は、令和2年度3台、令和3年度12台、令和4年度3台です。
保有台数に対して貸出台数が少ない理由としましては、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、各家庭においてWi-Fiを使用できる環境が普及していったものと考えています。
今後は家庭への貸出しだけでなく、校外学習などの学校の無線環境が届かない場所での教育活動で活用するなど、有効活用の方策を学校に示していきたいと考えています。
○副議長(小林章宏君) 柳 毅一郎君。
◆(柳毅一郎君) ありがとうございます。
こちらについてはぜひ有効活用、いろいろな活動で活用できるようにご検討いただければと思います。ありがとうございました。
それでは細目2、今後の整備の考え方になります。
冒頭といいましょうか、件名4の最初のときに申し上げたところなんですけれども、コロナということがあって随分このデジタル化、あるいは、何というんでしょうかね、自治体もそうですけれども、様々な民間でも変化があったと思います。その中で、今後のWi-Fiの整備について、一度どういう考えを持っているのか総括的に聞きたいと思います。
テザリングですとか、あとモバイル通信だけでも安定的に通信が可能となってきた部分もあったり、総合的な観点から今後の整備状況の考え方について浦安市の見解をお聞きしたいと思いますので、このWi-Fiについて、今まで様々整備計画を進めてきたと思いますけれども、一定の、コロナ禍があっていろいろ進んだ中での今現在の考え方をお示しいただければと思います。
よろしくお願いいたします。
○副議長(小林章宏君) 総務部長。
◎総務部長(山崎勝己君) 市では、これまで公衆無線Wi-Fiが災害時の通信手段としても有効であると考え、民間の公衆無線Wi-Fiの設置状況を勘案しながら、先ほどもご説明させていただいた公共施設に整備してきたところです。
しかしながら、近年パケット料金が安価となったことにより、公共施設での利用低下や民間の公衆無線Wi-Fiが縮小減少となるなど、公衆無線Wi-Fiをめぐる環境に変化が見受けられております。そのため、今後は利用状況などを見極めながら、設置場所など公衆無線Wi-Fi整備の在り方について検討していく必要があると考えております。
以上です。
○副議長(小林章宏君) 柳 毅一郎君。
◆(柳毅一郎君) ありがとうございました。いろいろこのWi-Fiについて聞かせていただきました。
様々やはりコロナ禍で変わったところもありますので、Wi-Fiに限らずですけれども、デジタル化については市民の皆様、あるいは議員の皆様、あるいは様々なところから意見があろうかと思いますので、しっかりと受け止めて、よりよきものにしていっていただきたいと思います。
それでは、最後になりますけれども、市民の皆様、そして市長をはじめとする当局の皆様、同僚の議員の皆様、この4年間、微力ながら私も浦安市のまちづくりを担わせていただけたこと、感謝申し上げまして、私の今期最後の一般質問を終了させていただきたいと思います。
どうもありがとうございました。
2023年07月03日
柳 毅一郎
令和4年市議会第4回定例会において自由民主党・無所属クラブを代表し、会派代表質疑を行いました。その議事録となります。

標題の通り自由民主党・無所属クラブを代表し会派代表質疑を行いました。
その内容となります。
動画はこちらから
※代表質疑
現に議題となっている議案等に対しその疑義をただすもので、議題となっている案件がなければ行うことができません。
代表質疑は会派(浦安では所属議員2人以上)の代表議員1名が行います。今回は、自身が会派を代表して質疑を行います。
以下内容概略及び目次となります。
【目次】
件名1 議案第2号 令和4年度浦安市一般会計補正予算(第6号)
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5億4,730万円を追加し、歳入歳出予算の総額を705億7,580万円としたものです。
1. 繰越明許について
2.債務負担行為の補正について
3. 物価高騰への対策事業について
① 浦安市障害福祉サービス事業所物価高騰対策支援給付金について
② 浦安市介護サービス事業所物価高騰対策支援給付金について
③ 私立保育所・幼稚園等物価高騰支援給付金について
④ 児童手当支給事業(加算分)について
➄ 浦安市公共交通事業者物価高騰対策支援給付金について
4. 市道幹線4号中央分離帯再整備事業について
5. ナラ枯れについて
件名2 議案第8号 浦安市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について
個人情報の保護に関する法律の施行に関し必要な事項を定めるため、制定するものですあり、その内容を質疑しました。
1. 改正の経緯について
2. 主な変更点及び影響について
件名3 議案第13号 浦安市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の制定について
地方公務員法の改正に伴い、職員の定年を引き上げ、管理監督職勤務上限年齢制および定年前再任用短時間勤務制を設けるとともに、60歳に達した職員の翌年度以後の給与に関する特例を設けるなどのため、所要の改正を行うものであり、その内容について質疑しました。
1.改正の背景
2.変化する主な事項について
件名4 議案第14号 浦安市自転車の安全利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について
千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の改正に伴い、自転車利用者の責務について、自転車損害保険などに加入することなどにより自転車に関する交通事故により生じた損害を賠償するため必要な措置をあらかじめ講ずるものとするため、改正を行うものであり、内容について質疑しました。
1.自転車保険の加入を義務とした理由
2.罰則について
3.今後の市の対応について
件名5 議案第18号 指定管理者の指定について(浦安市青少年交流活動センターの指定管理者)
浦安市青少年交流活動センターの指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議決を求めるものであり、内容について質疑しました。
1.指定管理者が変更となった経緯及び影響について
件名6 議案第19号 契約の締結について(美浜中学校校舎建築改修工事)
美浜中学校校舎建築改修工事を行うための工事請負契約について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議決を求めるものであり、その内容について質疑しました。
1.校舎建築改修の経緯について
2. 生徒への影響について
件名7 議案第20号 契約の締結について(総合体育館空調設備改修工事)
総合体育館空調設備改修工事を行うための工事請負契約について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議決を求めるものであり、内容について質疑をしました。
1.改修の経緯について
2.市民への影響について
3.大規模修繕計画について
4.スケジュールについて
以下、議事録全文となります。
これより会派代表者による総括質疑を許します。
初めに、自由民主党・無所属クラブ代表、柳 毅一郎君。
(柳 毅一郎君登壇)
◆(柳毅一郎君) おはようございます。
議長のお許しをいただきましたので、会派、自由民主党・無所属クラブを代表して、令和4年第4回定例会に上程されました議案に対する総括質疑を行います。
今回の令和4年第4回定例会には20議案が上程なされており、その内容について、配付されております発言通告書に沿って質疑をさせていただきたいと思います。
今回の補正予算としては、物価高騰対策が重要なものと考えております。コロナ禍における原油価格・物価高騰などが市民生活に大きな影響を与える中、国は令和4年度の予備費を活用し、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金を創設し、地方自治体に配分することとしました。今回、浦安市としても、この交付金を財源に何点か新規予算として計上されており、後ほどその内容についてお聞かせ願いたいと存じます。
それでは、質疑に移ります。
発言事項1、議案第2号、令和4年度浦安市一般会計補正予算案6号についてでございます。
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5億4,730万円を追加し、歳入歳出予算の総額を705億7,580万円とするものであり、その内容について、各委員会質疑につながるよう行ってまいります。
まず、要旨1、繰越明許についてです。
繰越明許は、継続費や債務負担行為が最初から複数年度にわたるものであるのに対し、経費の性質や予算成立後の何らかの理由でその年度内に支出を終わらない見込みがあるものについて、議会の議決を経て、翌年度に限り繰り越して使用できる予算を指します。今回、繰越明許について1点伺わせていただきます。
公共工事関係についてでございますが、公共工事関係の繰越理由としては、公共工事の工事量の繁閑に大きな差があり、工事の閑散期である4月から6月においては仕事が不足し、公共工事の従事者の処遇に悪影響が出るとか、また、繁忙期である1月から3月においては仕事量が増大することにより建築資材や労働者の確保等、準備、また様々多忙になってくるといったことで、施工時期の平準化等において様々懸念があります。そういったところについて繰り越されるといった理由も考えられますが、今回、昨年度と比較しまして、35款土木費について昨年同時期よりも多くの事業が繰越明許されていると読み取れます。
その主な要因について、総括的な説明を求めます。
次に、要旨2、債務負担行為についてでございます。
先ほど述べた繰越明許費は、当該年度内に事業が終わらず支出が翌年度になってしまう場合、その年度で確保していた予算を翌年度に繰り越すものでございますが、一方、債務負担行為は契約は今年度中に行い、実際の支出は翌年度以降に見込まれるものなど、あらかじめ承認するものでございます。
今回上程されたものの中で、2点質疑をさせていただければと思いますが、まず第1に、放課後うらっこクラブ運営費の債務負担行為補正の理由について、次に、公園植栽管理業務の債務負担行為補正の理由について、それぞれご答弁をよろしくお願いいたします。
次に、各種物価高騰への対策についてです。
要旨3、物価高騰への対策事業について。
冒頭に申したとおり、昨今の物価高への対策として、エネルギー、食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、地域の実情に合わせて必要な支援をきめ細やかに実施する地方公共団体の取組や対策を一層強化するため、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金が政府により創設されました。今回の補正予算においては、この国において創設された交付金を活用し、支援策を具体的に予算化したものであります。
今回、補正予算で計上されている金額としては、1億3,209万9,000円の予算となります。
今回、この物価高騰への対策として、本市においてもこの交付金を使った独自の予算化がなされております。物価高への対策については市民も関心が高いものと思われますので、まず1問目として、総括的に本市の物価高騰への対策事業について内容を質疑させていただきます。
次に、個別の事業に係る質疑については同様の趣旨が続くため、以下、一括でお聞きいたします。
まず、浦安市障害福祉サービス事業所物価高騰対策支援給付金1,200万円について、次に、浦安市介護サービス事業所物価高騰対策支援給付金1,580万円について、次に、私立保育所・幼稚園等物価高騰支援給付金1,125万円について、次に、児童手当支給事業の加算分8,885万9,000円について、最後に浦安市公共交通事業者物価高騰対策支援給付金419万円について、それぞれ事業の具体的な内容及び積算根拠について説明を願います。
次に、要旨4、市道幹線4号中央分離帯再整備事業について。
本件は、市道幹線4号中央分離帯再整備事業において、道路通行上の支障となっている老朽化した街路樹を撤去し、車両専用防護柵や立入防止柵を設置して安全対策を行うものでございますが、今回、当該事業を実施するに至った経緯及び事業内容について、そして整備スケジュールについても併せてお答えください。
要旨5、ナラ枯れについてでございます。
ナラ枯れとは、カシノナガキクイムシという害虫が媒介する菌が原因となって樹木が集団的に枯れる伝染病であります。被害が拡大すると倒木や景観の悪化などが懸念されます。数年前から市内の複数の場所で被害が確認されており、対応を図るものと考えておりますが、まず、本市の被害の状況について説明を願いたいと思います。
次に、発言事項2、議案第8号 浦安市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定についてです。
令和3年5月19日に、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が公布され、個人情報の保護に関する法律の一部改正が令和5年4月1日から実施されることとなりました。この個人情報保護法に関する法律の一部改正により、全国共通のルールとして、改正後の同法が地方公共団体にも適用されることに伴う条例の制定、改廃となっており、本市においても条例改正を行うところでございます。
そこで、まず条例制定に際し、個人情報保護法の一部が国で変更となった背景についてご説明願いたいと思います。
そして主な変更点、また、この改正が与える影響について、概要をご説明願いたいと思います。
次に、発言事項3、議案第13号 浦安市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の制定についてでございます。
地方公務員法の改正に伴い、職員の定年を引上げ、管理監督職の勤務上限年齢制及び定年前再任用短時間勤務制を設けるとともに、60歳に達した職員の翌年度以降の給与に関する特例を設けるなどのため、所要の改正を行うものであり、高齢化が進む中、ベテラン職員の能力や知見を最大限生かし、職員の育成の面でも活躍するためのものであろうかと推察いたしますが、まず、この法改正に至った背景についてご説明を願いたいと思います。
そして、本市において改正を行った際にどのような影響があるか、見解をお示しください。
次に、発言事項4、議案第14号 浦安市自転車の安全利用に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
全国的に、自転車が加害者となる事故で高額な損害賠償がされる事例が多く発生しております。被害者の救済や加害者の経済的負担の観点から、自転車保険に関してより一層の加入促進を図るため千葉県も対応を進めたと、一般的な理解としても推察するところでございますが、改めて、千葉県として自転車保険の加入を義務とした背景について伺います。
次に、発言事項5、議案第18号 指定管理者の指定について(浦安市青少年交流活動センターの指定管理者)でございます。
浦安市青少年交流活動センターの指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により議決を求めるものであり、その内容について、若干ではございますが、質疑させていただきます。
まず、今回、指定管理者が変更になっておりますが、その経緯について伺います。
そして、指定管理者の変更による変化についてどのようなことを考えられているのか、その点、当局のお考えをお伺いさせていただきます。
次に、発言事項6、議案第19号 契約の締結について、美浜中学校校舎建築改修工事を行うための工事請負契約についてでございますが、こちらも議会の議決を求めるものであり、その内容について、いささかではありますが、質疑させていただきます。
まず、本件は施設の老朽化対応であることは推察しておりますが、改めて今回こちらも、美浜中学校の校舎建築改修工事を行うことになった経緯についてお伺いします。
そして、工事による生徒たちへの影響について懸念はないか、それぞれお伺いいたします。
次に、発言事項7、議案第20号 契約の締結について(総合体育館空調設備改修工事)でございます。
総合体育館については、皆様ご承知のとおり、東京ディズニーリゾートに隣り合う浦安市運動公園にある体育館であります。着工は1993年2月、竣工は1995年7月の地上5階、地下2階でありまして、巨大なメインアリーナを中心に第1武道場、第2武道場、弓道場、トレーニング室などを備える大変立派な施設であり、本市が自慢のできる施設ではないかと思っております。その一方で、今後、その維持・補修等について大きな金額がかかってくることは中長期的に考える必要があります。
そこで、今回、空調設備改修も全体改修の一部として計上されていると考えますが、まず、総合体育館の老朽化についての見解を踏まえた上で、空調設備改修の経緯をお示ししていただきたいと思います。
以上、1回目の質疑とさせていただき、以降は質問者席から行わせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(宝新君) 市長、内田悦嗣君。
(市長 内田悦嗣君登壇)
◎市長(内田悦嗣君) おはようございます。
自由民主党・無所属クラブ、柳 毅一郎議員の総括質疑にお答えいたします。
私からは議案第2号、物価高騰への対策事業について、詳細につきましては、積算根拠、内容等については後ほど担当よりお答えいたしますので、私のほうからは、総括的な考え方についてご答弁させていただればと思います。
物価高騰の対策としましては、国においてエネルギー、食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、地域の実情に合わせて必要な支援をきめ細やかに実施するため、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金が創設されるなどの対策が講じられてきたところでございます。
本市におきましても物価高騰等により市民や事業者への影響が見込まれることから、国や県が行う事業を考慮し、国が推奨する事業メニューを参考としながら、低所得や子育て世帯、保育施設、福祉サービス事業者、また公共交通事業者への負担軽減等を目的に、臨時交付金を活用し、市独自の物価高騰対策事業を実施することとしたものでございます。
先ほど申し上げたとおり、内容、積算根拠等については担当よりお答えします。
また、他の質疑につきましても担当よりお答えいたします。
○議長(宝新君) 財務部長。
◎財務部長(泉澤昭一君) 私からは、発言事項1、議案第2号の中から1点お答えいたします。
要旨1、繰越明許についての中、土木費について、昨年度よりも多くの事業が繰越明許となっているが、その要因についてのお尋ねです。
土木費の繰越明許につきましては、働き方改革の一環として令和元年に改正された公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づき、公共工事の施工時期の平準化を図るため、12月補正に予算を計上するとともに繰越明許費を設定したところでございます。
また、その他の事業につきましても、千葉県や関係者との協議に時間を要する事業が増えたことによりまして、昨年度に比べ繰越明許費の設定が増加しているということでございます。
以上でございます。
○議長(宝新君) 健康こども部長。
◎健康こども部長(野崎雄大君) 私のほうからは5点、質疑にお答えさせていただきます。
まず1点目、発言事項同じく要旨2、債務負担行為の補正についての中、放課後うらっこクラブ運営費の債務負担行為の補正を行うことになった理由についてというお尋ねでございます。
放課後うらっこクラブ運営費の債務負担行為の補正を行うこととなった主な理由は、児童育成クラブの入会児童数の増加に伴い児童室を追加したことや、特別な支援が必要となる児童の増加などにより放課後児童支援員を増員する必要が生じたため、経費が増額となったことによるものでございます。
続きまして要旨変わりまして3、物価高騰への対策事業についての中、私立保育所、幼稚園等物価高騰支援給付金の内容及び積算根拠についてでございます。
私立保育所や幼稚園等に対する運営費に要する経費の一部を給付するものとして、その内訳としましては、定員規模に応じて定員25人までの13園に5万円、50人までの9園に10万円、100人までの21園に20万円、150人までの5園に30万円、151人以上の10園に40万円を支給するものとし、総額1,125万円を計上したものでございます。
続きまして、同じく要旨、児童手当支給事業(加算分)における内容と積算根拠でございます。
本事業につきましては、令和5年1月分の児童手当受給者を対象として、2月支給分に5,000円を加算して支給するもので、支給対象児童を1万7,350人と見込み、補助金として8,675万円、振込手数料として122万1,000円、郵送代として88万8,000円、合計8,885万9,000円を計上いたしました。
続きまして、発言事項変わって5、議案第18号、要旨1、指定管理者が変更となった経緯及び影響についての中、指定管理者変更の経緯についてでございます。
青少年交流活動センターにつきましては、現在、アクティオ株式会社が指定管理者となっておりますが、令和4年度末をもって指定管理期間が満了することから、令和5年度以降の指定管理者の公募を本年8月に行ったところ、3者の応募がありました。この3者に対し10月に選定等審査会による審査を実施した結果、提案内容や5年間の指定管理料が他者と比較して優れていた株式会社オーエンスを次期指定管理者の候補として決定したものでございます。
続いて、要旨同じく指定管理者変更による変化について、どのようなことが考えられるかというお尋ねでございます。
指定管理者の候補として決定した株式会社オーエンスにつきましては、他の自治体の類似施設において運営実績があり、予約方法の改善提案がなされるなど、宿泊サービスにおいて利用者の利便性向上が図られることが期待されるほか、自主メンテナンスの実施による経費の削減効果などが見込まれております。
なお、指定管理者の変更によるサービス低下等の影響はないものと考えておりますが、事業者間での引継ぎが円滑に行われるよう、市としても注視してまいります。
以上でございます。
○議長(宝新君) 都市整備部長。
◎都市整備部長(知久岳史君) 私からは、発言事項1、議案第2号の中から4点についてお答えいたします。
要旨2、債務負担行為の補正についての中、公園植栽管理業務の債務負担行為補正の理由についてのお尋ねです。
公園植栽管理業務につきましては、当初予算成立後に入札を行っておりましたが、雑草の繁茂が著しい4月に除草作業を行うことが難しいことから、令和4年度内に入札を行い4月に除草作業が実施できるよう、債務負担行為補正を行うものです。
次に、要旨変わりまして要旨4、市道幹線4号中央分離帯再整備事業についての中、事業を実施するに至った経緯及び事業内容についてのお尋ねです。
経緯といたしましては、市道幹線4号の東野交差点付近から見明川丁字交差点までの約1.6キロメートルの区間において、中央分離帯の街路樹の車道へのせり出しや横断歩道以外での歩行者の横断など、危険な状態にあることから、市では部分的な横断防止柵設置や支障街路樹の緊急的な剪定等を実施してまいりましたが、抜本的な改善を図るため、中央分離帯の再整備を行うものです。
事業内容といたしましては、植樹後40年以上が経過し剪定での管理が困難となっている街路樹を撤去するほか、交通安全施設として車両用防護柵や立入防止柵などの設置を行うものです。
続きまして同じ要旨の中、スケジュールについてのお尋ねです。
市道幹線4号中央分離帯再整備事業につきましては、令和5年度での実施を予定しておりましたが、公共工事の施工時期の平準化の観点や早急に安全対策を講じる必要があることから、令和4年度に増額補正をし、対象区間全域の設計を行うとともに、東野交差点付近から東海大浦安入口交差点までの工事について、早期発注に取り組みます。
また、残りの区間につきましても順次整備していきたいと考えております。
続きまして要旨5、ナラ枯れについての中、本市の公園、緑地などでの被害状況についてのお尋ねです。
公園でのナラ枯れの被害状況につきましては、中央公園や美浜公園、見明川公園などで約40本、また、緑地や街路樹では湾岸緩衝緑地やシンボルロードで約60本の被害樹木を確認しているところです。
私からは、以上です。
○議長(宝新君) 福祉部長。
◎福祉部長(高梨誠二君) 私からは、発言事項1、議案第2号の中から2点お答えいたします。
要旨3、物価高騰への対策事業についての中、浦安市障害福祉サービス事業所物価高騰対策支援給付金について、内容及び積算根拠についてのお尋ねです。
障害福祉サービス事業所の運営に対する給付金でありまして、内訳としましては、事業所の種別に応じて計画、相談、支援等の相談系サービスの事業所に10万円、居宅介護や生活介護等の居宅・通所系サービスの58事業所に20万円を支給するものとし、総額で1,200万円を計上したものです。
次に、同じ要旨の中、浦安市介護サービス事業所物価高騰対策支援給付金についての内容及び積算根拠についてのお尋ねです。
介護サービス事業所の運営に対する給付金でありまして、内訳としましては、事業所の種別や規模に応じて居宅介護支援及び福祉用具の14事業所に10万円、訪問系サービス及び小規模通所系サービスの40事業所に20万円、大規模通所系サービスの12事業所に30万円、居住系サービスの7事業所に40万円を支給するものとして、総額で1,580万円を計上したものです。
以上でございます。
○議長(宝新君) 都市政策部長。
◎都市政策部長(板橋栄一君) 私からは発言事項1、要旨3の中、浦安市公共交通事業者物価高騰対策支援給付金の内訳及び積算根拠についてお答えをさせていただきます。
本給付金は、市内の事業所で保有もしくは管理し、運行している事業用自動車の台数に応じ、高速バスや深夜バス等を除く一般路線バス1台当たり2万円、タクシー1台当たり1万円を交付するものです。内訳としましては、バスの2事業者に210万円、個人タクシーを含むタクシーの17事業者に209万円として想定し、総額419万円を計上したものです。
以上となります。
○議長(宝新君) 総務部長。
◎総務部長(山崎勝己君) 私からは、4点お答えいたします。
初めに発言事項2、議案第8号、要旨1、改正の経緯についての中、条例制定に際し、個人情報保護法が変更となった背景についてのお尋ねです。
これまで個人情報の保護に関して、全国の地方公共団体等が独自に定めた条例を有しており、個人情報に対する定義や解釈等に差異が生じていることが、医療や災害対策などに向けた個人データの広域連携や利活用を阻む大きな要因の1つと考えられてきたところです。このような背景から、個人情報の保護、利活用に関し全国的な共通ルールを適用することを目的として個人情報の保護に関する法律の改正が行われ、令和5年4月1日以降、国の個人情報保護委員会の所管に一元化されることとなっております。
この法改正に伴い、本市の個人情報保護制度の運用に関わる一定の事項につきましては、条例に委任及び規定することが許容されております。そのため、今回、浦安市個人情報の保護に関する法律施行条例を制定するものです。
続きまして要旨2、主な変更点及び影響についての中、変更点、改正が与える影響の概要についてのお尋ねです。
法改正による主な変更点といたしましては、重大な個人情報の漏えい時において国の個人情報保護委員会への報告、漏えい情報の本人に対する通知の義務が課せられること等が挙げられます。
また、法改正による影響といたしましては、デジタル社会の進展という状況下において官民を通じた個人情報保護制度の見直しが行われ、個人情報の保護と利活用の両立が図られることが考えられております。
続きまして、発言事項変わりまして議案第13号、要旨1、改正の背景の中、条例改正に至った背景についてのお尋ねです。
公務員の定年引上げにつきまして、国では、少子・高齢化が進み生産年齢人口が減少する中で、複雑・高度化する行政課題への的確な対応などの観点から、60歳以降の職員を活用しつつ次の世代にその知識、技術、経験などを継承していく必要があるとの考えから、定年引上げ等のため、令和3年6月に地方公務員法を改正したところです。本市におきましても法改正の趣旨を踏まえて、浦安市職員の定年等に関する条例等の一部を改正するものです。
続きまして要旨2、変化する主な事項についての中、定年引上げによる影響についてのお尋ねです。
60歳以降の職員が引き続き働き続けることにより、健康上、人生設計上の理由等により多様な働き方を可能とすることへのニーズが高まるものと考えております。また、財政面におきまして、定年引上げ後の給料月額は60歳時点での給料月額の7割水準とされており、これまでの再任用制度の給料月額と比べて増額していくと見込んでおります。
以上です。
○議長(宝新君) 市民経済部長。
◎市民経済部長(杉山正毅君) 私からは、発言事項4、議案第14号から1点お答えいたします。
要旨1、自転車保険の加入を義務とした理由の中、千葉県が自転車保険の加入を義務とした背景についてのお尋ねです。
千葉県が自転車損害賠償保険の加入を義務づけた背景につきましては、県内の当該保険の加入率が6割程度であり、近年発生する自転車運転者が加害者となる事故では高額な損害賠償請求がされる事例が多く発生しているところです。これらの状況を受け、被害者の救済及び加害者の経済的負担等の観点から、自転車損害賠償保険に関してより一層の加入促進を図るため、条例の一部を改正し、加入を義務化したものでございます。
以上です。
○議長(宝新君) 教育総務部長。
◎教育総務部長(丸山恵美子君) 私からは、発言事項6、議案第19号から2点お答えいたします。
要旨1、校舎建築改修の経緯についてのお尋ねです。
学校校舎につきましては、令和2年度に策定した浦安市学校施設長寿命化計画に基づき、築30年が経過した施設について、施設の安全性の確保や老朽化などに対応するため、順次改修工事を行っているところです。
美浜中学校につきましては昭和59年度に建設され、37年が経過しており、令和3年度に校舎の点検を行った結果、屋上防水層のはがれや壁面のひび割れなど建物の老朽化が見られたことから、屋上防水、外壁、内装の改修、床や天井の改修、昇降機の補修などの工事を行うものです。
続きまして要旨2、生徒への影響についてのお尋ねです。
本工事は、これまでの学校改修工事と同様に、基本的には夏期休業期間を中心に工事を行うスケジュールとなります。詳細な工程につきましては、今後、請負業者や学校と打合せを行い決めていくこととなりますが、夏期及び冬期休業期間だけでは工事を終わらせることはできませんので、授業を行っている期間につきましても、学習活動の妨げとならないよう騒音や振動等、十分配慮しながら工事を進めていきます。
以上です。
○議長(宝新君) 生涯学習部長。
◎生涯学習部長(増田丈巳君) 私からは、発言事項7、議案第20号から1点お答えいたします。
総合体育館の改修の経緯についてのご質疑です。
総合体育館は平成7年の竣工後、27年目を迎え、この間に建築、電気、及び今回改修工事を行う空調設備を含めた機械設備につきましても部品交換等を行いながら維持・保全に努め、施設の運用を図ってきたところです。また、空調設備につきましては、平成27年度に全11系統あるエアハンドリングユニットのうち4系統の更新を行い、今回、残りの7系統のうち、老朽化が著しい4系統と還風機5系統及び自動制御機器の更新を行うものです。
以上です。
○議長(宝新君) 柳 毅一郎君。
◆(柳毅一郎君) それぞれご答弁ありがとうございました。
それでは、2回目の質疑を行います。
発言事項、議案第2号 令和4年度浦安市一般会計補正予算(第6号)の中、要旨5、ナラ枯れについてでございますが、先ほど答弁として、公園でのナラ枯れあるいは緑地や街路樹のところにそれぞれ被害が出ているということをお示しいただきましたが、その被害状況を受けて今回補正予算を計上していると思いますけれども、今後、市がどのようなことをやるのか、補正予算後の対応についてお伺いしたいと思います。
次に、発言事項4、議案第14号 浦安市自転車の安全利用に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
先ほど千葉県として自転車保険の加入を義務とした背景について、こちらもご説明をいただきましたが、関連で何点か質疑をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
今回「義務」という名称がございますが、こちらについて、保険加入をしないことについて罰則等、何かございますでしょうか。どのような見解か、出されている見解をお示しください。
そして、条例施行後の市の対応についてです。この条例ができて、市として具体的に何をしていくのかお示しいただければと思います。
次に、発言事項7、議案第20号 契約の締結について(総合体育館空調設備改修工事)でございます。
こちらも先ほどご答弁、ありがとうございました。
こちらについては、やはり利用者も大変多い施設でございますので、今回の工事が総合体育館の利用者へ与える影響等を聞かせていただきたいと思います。具体的な質疑の内容として、まず、個人による市民への影響について、例えばこちら、工事が行われることによって何か利用の制限がかかるといったことがあるのか、そういったことも含め、可能であれば答えていただければと思います。
次に、実施計画で示されております、総合体育館の老朽化に計画的な修繕をしようという形で方針が示されておるところでございますが、この大規模修繕計画について、まず概要を説明していただきながら、今回の工事は今後、大規模改修に必要となる改修工事のうちどの程度施設維持において重要なのか、説明を願いたいと思います。
そして最後に、スケジュールについてでございます。
工事による市民への影響についても聞きましたが、どのように具体的にこの工事が進行するか、利用者にとっても関心が高いのではないかと思いますので、今回、総合体育館空調設備改修工事のスケジュールについて、確認のためお伺いさせていただきます。
以上、2回目とさせていただきます。こちらもよろしくご答弁をお願いします。
○議長(宝新君) 都市整備部長。
◎都市整備部長(知久岳史君) 私からは、議案第2号の中から1点についてお答えいたします。
要旨5、ナラ枯れについての中、被害樹木への今後の対応といったお尋ねです。
ナラ枯れにより枯死した樹木につきましては、内部にナラ菌を媒介するカシノナガキクイムシが繁殖しているため、樹木を伐採し、粉砕及び焼却処分を行います。また、ナラ枯れの被害につきましては全国的には令和2年度に急増し、その後、減少している状況ですが、今後もパトロールや調査を行い、状況の把握に努めてまいりたいと考えております。
以上です。
○議長(宝新君) 市民経済部長。
◎市民経済部長(杉山正毅君) 私からは、議案第14号から2点お答えいたします。
要旨2、罰則についての中、保険加入しないことで罰則の見解についてのお尋ねでございます。
千葉県の条例同様、保険未加入者に対する罰則はありませんが、被害者のみならずご自身やご家族を守るため、自転車損害賠償保険に加入していただきたいと考えております。
次に、要旨3、今後の市の対応についての中、条例施行後の対応についてのお尋ねです。
条例施行後の対応としましては、市広報紙、ホームページ、ツイッターなどを活用しての広報活動を行うほか、自転車小売業者などと連携しチラシなどを配布するとともに、浦安警察署や関係団体と行う早朝指導や自転車安全指導において、保険の加入促進に努めてまいりたいと考えております。
以上です。
○議長(宝新君) 生涯学習部長。
◎生涯学習部長(増田丈巳君) 私からは、議案第20号から3点お答えいたします。
まず、市民への影響というお尋ねです。
工事による市民への影響につきましては、空調機器の各系統ごとの部屋が約1か月半程度使用できない予定です。具体的には、サブアリーナ、多目的室、トレーニング室、エントランスの一部となります。また、メインアリーナ系統は休館日を利用し改修を行う予定ですが、体育館棟及びプール棟の全てがそれぞれ1週間程度、また、全館使用停止期間が3日程度を予定しております。時期的には、令和6年1月から7月までの範囲内で使用の制限が出る見込みとなっております。
続きまして大規模改修計画について、その概要と施設維持について、今回のこの工事が重要なのかというようなお尋ねです。
大規模修繕計画については、社会体育施設の計画的な修繕や改修を行うため、建築物及び設備の現況調査を行い、劣化度を評価した上で修繕や改修の必要性を判断するものです。また、調査によって確認された諸課題を整理し、効率的かつ効果的に修繕や改修を行うに当たり、スポーツ庁が策定したスポーツ施設適正化ガイドラインに沿って改修計画を策定するものです。
今回改修する空調設備についても、今後の修繕計画に反映されるものですが、空調設備が作動しなくなった場合、長期間施設を使用できなくなることから、本工事は施設維持において、予防保全を行うため非常に重要なものと考えております。
続きまして、今後のスケジュールというお尋ねです。
本工事の改修のスケジュールにつきましては、令和5年1月から12月にかけて機器の製作を行い、令和6年1月から6月にかけてエアハンドリングユニット及び自動制御機器を更新し、同年7月に総合試運転及び竣工検査を行う予定となっております。
以上です。
○議長(宝新君) 柳 毅一郎君。
◆(柳毅一郎君) ありがとうございました。
それでは、以降は各常任委員会での質疑に委ねたいと思います。
以上で会派、自由民主党・無所属クラブを代表しての私・柳 毅一郎の代表質疑を終わります。
ご答弁ありがとうございました。
2023年02月19日
柳 毅一郎

